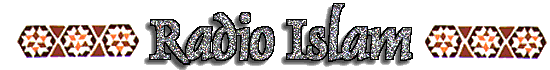ユダヤ民族3000年の悲劇の歴史を真に解決させるために
電網木村書店 Web無料公開 2000.6.2
第1部:解放50年式典が分裂した背景
第1章:身元不明で遺骨も灰も確認できない
「大量虐殺事件」4
【原著p73写真:3元収容所司令官ホェスの展示説明
【原著p74写真:4ホェスが絞首刑に処せられた場所】
ホェスを「拷問」した英国籍ユダヤ人軍曹の確信犯的「自慢」
フランスの歴史家フォーリソンは、「イギリスはどうやってルドルフ・ホェスの告白をえたか」(『歴史見直しジャーナル』86~87冬)という題名の論文で、くわしい分析をしている。
ホェスは最後にポーランドのクラコウで裁判にかけられ、一九四七年四月一七日にアウシュヴィッツ収容所内(写真3,4.Web では省略)で処刑されたが、その死の直前に書いたとされている「回想録」には、つぎのような部分がある。
「わたしは一九四六年三月一一日に逮捕された。[中略]わたしにたいする最初の尋問における証言は、わたしをなぐってえたものである。わたしはサインはしたが、そこになにが書かれてあるのかは知らない。アルコールと鞭でわたしはまいってしまった。鞭はわたしのものだが、偶然、妻の荷物のなかにはいっていた。それは馬にふれたことすらなく、ましてや収容者にむけられたことなど、まったくなかったというのに」
わたしの手元には、フォーリソンが引用した英語の原文のとおりの『アウシュヴィッツの司令官/ルドルフ・ホェスの自伝』の英語版のコピーがある。この箇所は、日本の研究者にとって重大な問題をはらんでいる。
なぜなら、日本語訳の『アウシュヴィッツ収容所/所長ルドルフ・ヘスの告白遺録』でも、イギリス軍による最初の尋問について、「調書に署名はしたものの、それに何と書いてあるか私は知らない」となっている。だがなぜか、「わたしをなぐってえたもの」という決定的な箇所に相当する部分がかけているのだ。しかも、「私の最初の取り調べがはじめられた」の前に、「決定的な証拠にもとづいて」という英語版にはない字句がくわわっている。
訳者の序文には「全訳」とあるが、そうだとすればその元のドイツ語の原文があやしい。決定的な部分の削除と追加による情報操作の疑いがある。「歴史見直し研究所」でウィーバーに質問したところ、その版は手元にないがドイツ語のテキストには問題がおおいということだった。この件はまだ追跡調査が必要である。
日本語訳の『アウシュヴィッツ収容所/所長ルドルフ・ヘスの告白遺録』には、この直後に、つぎのような英語版と基本的に一致する部分がある。
「数日後、私は、英軍占領地中央取調機関のある、ウェーゼル河畔ミンデンに送られた。そこでも、私は、英軍首席検察官(陸軍少佐)にいっそういためつけられた。刑務所も、この扱いに応じたものだった」
文中の「いっそういためつけられた」は、私の訳では、「さらに乱暴なとりあつかいをうけた」である。この部分の「さらに」は、さきの部分の「証言はわたしをなぐってえたもの」の内の「なぐって」がなければ意味をなさない。また、「検察官」の仕事なのだから、「乱暴なとりあつかい」の目的は、それで尋問の効果をあげて、ねらいどおりの「証言」をえること以外にはないはずである。
フォーリソンの前記論文では、ホェスの手記の公開の仕方自体をも問題にしている。それによると、公開は「やっと11年後」であり、西ドイツ(当時)国立現代史研究所のマーティン・ブロシャット所長の編集の仕方は、「学問的方法を無視」したものである。
ホェスの尋問調書の一つは英語でタイプされており、下部にホェスのサインがある。本人の母国語のドイツ語でないだけでも大いに偽造の疑いがあるが、ホェスの尋問にあたったイギリス軍の尋問者自身が、のちに拷問の事実をみとめている。
ホェスを逮捕し、尋問したイギリス軍の軍曹、バーナード・クラークは、イギリス国籍のユダヤ人だった。わたしはさきに紹介したフォーリソンの論文、「いかにしてイギリスはルドルフ・ホェスの告白をえたか」によって、その拷問の経過を知った。出典は一九八三年に発表された『死の軍団』という本で、著者、ルパート・バトラーはクラークとインタヴューしている。『死の軍団』はすでに絶版で入手は不可能だが、これも「歴史見直し研究所」のウィーバーにたのんでおいたら、帰国してから該当部分のコピーをおくってくれた。表紙の部分を見ると、カナダのトロント州、オンタリオ地方裁判所のゴム印がおされていて、名前や日付などが手がきでしるされている。のちにくわしく紹介する「ツンデル裁判」の書証のコピーであった。
ルパート・バトラーによると、クラークには拷問について「なんら後悔をしめさない。それどころか正反対に、“ナチ”を拷問したことについてかなり自慢した」という。いわゆる確信犯である。
クラークが目的とした「すじのとおった供述」をえるまでには「三日間の拷問が必要だった」。ホェスが調書にサインした時刻は午前二時三〇分だった。バトラーは、「尋問でもっともくるしんだのは捕虜ではなくてバーナード・クラークのほうだった」という奇妙な書きかたをしている。その理由は、クラーク自身の言葉としてしるされているが、つぎのようである。
「逮捕の前には、わたしの髪の毛は真っ黒だった。その三日後には突然、まんなかに白いすじがあらわれた」
クラーク軍曹はまた、一農夫の姿で身をひそめていたホェスの捜査にあたって、ホェスの妻を子供からひきはなして尋問したが、そのさいには暴力は「まったく必要ではなかった」。決め手は、あれこれと長いなだめすかしの最後に、つぎのようにどなりつけたセリフだった。
「白状しないと、おまえらをロシア軍にひきわたす。やつらはおまえを銃殺隊のまえにひっぱりだす。息子はシベリア送りになるぞ」
三日間のホェスの尋問にあたって、クラークが、どういうおどしのセリフをつかったかはさだかでない。だが、ホェスの妻を最後におとした「息子はシベリアおくりになるぞ」という自慢の台詞をクラークが遠慮してつかわなかったという状況は、想像するほうが困難である。しかも、この「シベリアおくり」または「ロシア軍にひきわたす」というおどし文句は、クラーク軍曹の独自の思いつきではなかった可能性が非常にたかいのである。
ニュルンベルグ裁判についての最新の総合的な研究として見のがせないのは、『歴史見直しジャーナル』(92夏)に編集長のマーク・ウィーバーがみずから執筆した五六ページの大論文、「“戦争犯罪”裁判は絶滅政策を立証したか?/ニュルンベルグ裁判とホロコースト」(以下では「ニュルンベルグ裁判とホロコースト」に省略)である。
ウィーバーによれば、ニュルンベルグ裁判で死刑を宣告された元労働大臣ザウケルは、「妻と子どもをソ連にひきわたす」とおどかされて「罪の告白」に署名をし、のちにそのおどしをうけた事実を公表した。国際検察局のボスのケンプナー検事は、元ドイツ外務省高官のガウスから同僚を告発する証言をひきだすために、「ソ連にひきわたして絞首刑にさせる」というおどし文句をつかっていた。
シュテークリッヒ判事の『アウシュヴィッツ/判事の証拠調べ』にも、バッツ博士の『二〇世紀の大嘘』にも、やはり、おなじ「おどし文句」の指摘がある。
イギリス軍による拷問の事実についても、ウィーバーは二例を紹介している。一例は、アウシュヴィッツ時代のホェスの副官で、その後、ビルケナウ(アウシュヴィッツ第二収容所)の司令官、ベルゲン・ベルゼン収容所司令官などを歴任したヨーゼフ・クラマーにたいしての拷問である。もう一つの例は、収容所全体の管理責任者で、親衛隊の経営管理本部長だったオズヴァルド・ポールにたいする拷問である。ポールはイギリス軍に逮捕された際、椅子にしばりつけられて失神するまでなぐられ、歯を二本うしなった。