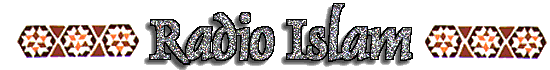ユダヤ民族3000年の悲劇の歴史を真に解決させるために
電網木村書店 Web無料公開 2000.6.2
第1部:解放50年式典が分裂した背景
第1章:身元不明で遺骨も灰も確認できない
「大量虐殺事件」7
美化されすぎてきた「ニュルンベルグ裁判」への重大な疑問
ニュルンベルグ裁判の資料を図書館のコンピュータでさがしていたら、『「ニーュルンベルグ裁判」を見て』という項目がでてきた。戦争体験にこだわりつづける戦中派作家、大岡昇平が、東京新聞(61・3・5~6)によせたみじかい随想なのだが、その後、『証言その時々』という単行本におさめられている。
大岡はまず、ニュルンベルグ裁判自体について、「映画に現われた限り、東京裁判よりはるかに公正に行われたらしいが、いずれにしても戦勝国が敗戦国を裁くのだから、公正なんてものがあるはずがない」という、一歩距離をおいた姿勢をしめす。ところが、このスタンリー・クレーマー監督作品のすじがききをおって紹介するうちに、「これは現代アメリカの一部の良心を代表した映画ということができるだろう」という評価をくだしてもいる。
だが、当然のことながらハリウッド製フィクションの『ニュルンベルグ裁判』には、被告の拷問というシーンはまったくでてこなかった。この映画の舞台はおなじニュルンベルグ裁判所ではあるが、内容は主要な軍事法廷ではなくて継続裁判の一つである。それでも、おおくの映画ファンにとっては、ニュルンベルグ裁判の全体像の代用品になってしまっているだろう。
偶然か、それともやはり戦後五〇年の節目を意識してであろうか、NHKの衛星放送第二の「ミッドナイト映画劇場」が、一九九四年一一月一九日と二六日に、この『ニュルンベルグ裁判』を二部にわけて放映した。この作品も、一九六一年の製作なのに『シンドラーのリスト』と同様、モノクロでドキュメンタリー・タッチをねらっていた。とりあえず実物を見ていない読者のために、このハリウッド映画の主な出演者だけを紹介しておこう。
スペンサー・トレシー、バート・ランカスター、リチャード・ウィドマーク、マリーネ・ディートリッヒ、マキシミリアン・シェル、ジュディ・ガーランド、モンゴメリイ・クリフト。いずれもまさに堂々たる国際的な主役級の大スターである。
さて、さきのシンプソン陸軍委員会が調査したダッハウのマルメディ裁判のさいのような拷問の事実が、これまでまったく報道されていなかったのかというと、決してそうではない。『ニュルンベルグ裁判/ナチス戦犯はいかに裁かれたか』という本がある。著者は、ドイツ人の現代史家、ウェルナー・マーザーである。こちらの日本語版「訳者あとがき」には、つぎのような、さきの大岡のとは正反対の感想がしるされている。
「私たちの東京裁判を、人種的偏見にみちた復讐裁判だとする意見があるが、ナチス第三帝国崩壊後のドイツ指導層の受けた侮辱と冷遇とつき合わせてみると、なんとマッカーサーの軍隊は『紳士的』であったことかと今さらのように驚いてしまう」
以下、その一部を紹介しよう。
ポーランド総督だったハンス・フランクが「受けた侮辱と冷遇」の場合は、簡単な一行の記述だけである。かれは「ミースバッハの市立刑務所に送られたが、ここで、二人の黒人アメリカ兵にサディスティックに殴打され」ている。
反ユダヤ主義の週刊誌『突撃兵隊』の発行者だったユリウス・シュトライヒャーの場合には、本人の自筆の報告ものこされており、つぎのような大変にくわしい記述がある。
「シュトライヒャーがのちに主張したところによると、彼が回り道をしてニュルンベルグに連行された時、ユダヤ人たちは彼に屈辱を与え、残酷に拷問し、殴打したという。彼がニュルンベルグで、弁護人ハンス・マルクス弁護士に渡した自筆の報告には、特にこう書かれている」
以下は、その「自筆の報告」の一部である。
「(前略)新聞記者(五分の四がユダヤ人)の前で私は嘲罵を受けました。(中略)その夜一晩、ユダヤ人から私は嘲弄された。(中略)私に残されているのはシャツとズボンだけである。おそろしく寒かった。(中略)北向き。もっと寒くなるように窓は引き開けられていた。二人の黒人が私を裸にし、シャツを二つに引き裂く。私はパンツだけになった。私は鎖でしばられているので、パンツが下がっても上げることができなかった。そして私は素っ裸にされた。四日間も! 四日目に私の体は冷えきって感覚がなくなった。もう耳も聞こえなかった。二~四時間ごとに(夜も)黒人たちが来て、一人の白人の命令のもとで私を拷問した。乳首の上を煙草の火で焼く。指で目窩を押す。眉毛や乳首から毛を引きむしる。革の鞭で性器を打つ。睾丸ははれ上がる、つばを吐きかける。″口を開け!″そして口の中につばを吐く。もう私が口を開けないでいると、木の棒でこじ開ける~~そしてつばを吐き込む。鞭で殴打。たちまち体中に血でふくれ上がった筋が走る。壁に投げつける。頭を拳固で殴打。地べたに投げつける。そして背中を鎖で打つ。黒人の足にキスすることを私が拒否すると、足で踏みつけ、鞭打ち。腐った馬鈴薯の皮を食うのを断ると、再び殴打、つば、煙草の火! 便所の小便を飲むことを拒否すると、またも拷問。毎日ユダヤ人記者が来る。裸の写真をとる! 私に古ぼけた兵隊マントをかけて嘲弄。(中略)四日間休みなくしばられたまま。大小便もできない。(後略)」
同書のこの部分では、「こういう取り扱いを受けたのは~~記録や個人的情報によれば~~明らかにハンス・フランクとユリウス・シュトライヒャーだけだった」としているが、この判断は「明らかに」まちがいである。二度あることは三度ある。しかも、同書のなかの別の部分にさえ、これ以外の「侮辱」「強要」「殴打」「拷問」の事実が、いくつかしるされているのである。
「侮辱」については、ドイツ降伏のしりぬぐい役をつとめた臨時政府、海軍提督デーニッツの閣僚と軍首脳も例外ではなかった。船上で政府と軍の解体と逮捕の通告をうけた直後のことである。同書では、この経過を以下のようにしるしている。
「デーニッツとその随員は船を立ち去ったが、そのあとイギリス兵たちは会談の始まるはずの外務省の会議ホールに殺到した。すべてのドイツ人は真っ裸に引きむかれ、屈辱に満ちた身体検査を耐え忍ばなければならなかった。それは同時に一つ一つの部屋で、将校や秘書孃に対してさえも行われた。イギリス兵は俘虜たちから時計、指輪、その他金目のものを盗みとり、一同は両手をあげたまま中庭につれ出された。そこでは二、三〇人の新聞記者が、この「大興行」を待ち受けていて、ズボンもはいていない将官や大臣の写真をとった。「第三帝国は今日死んだ」と、一九四五年五月二十四日の『ニューヨーク・タイムズ』紙は、この下品な見世物にコメントをつけた」
閣僚や軍首脳にたいしてさえ、こんな状況だったのだから、むしろ、侮辱と拷問をうけなかった例のほうが、めずらしかったのではないだろうか。しかもさらに、裁判のすすめかたにも重大な疑問が生じてきた。