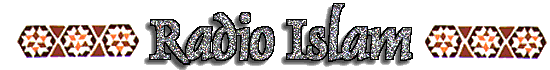ユダヤ民族3000年の悲劇の歴史を真に解決させるために
電網木村書店 Web無料公開 2000.7.4
第3部 隠れていた核心的争点
「マスコミ・ブラックアウト」の陰で進んでいた科学的検証
【原著p187写真:アウシュヴィッツ第2キャンプ、ビルケナウの「ガス室」跡】
一九四九年には、アメリカの上院でシンプソン陸軍委員会の報告書が公表された。わたしの手元には、A4判でびっしり二四ページにもおよぶ議事録がある。
報告書は、ドイツのダッハウでおこなわれた捕虜にたいする数々の拷問が、いつわりの自白を引きだし、判決をゆがめるにいたったことを認めていた。シンプソンらは、まだ生存中の死刑囚にたいしての減刑をもとめていた。だが、減刑も再審も実行されなかった。それどころか、……
「報告書を提出した以後にも、減刑をもとめた対象のうちの五名にたいして絞首刑が執行された。全部で、調査対象とした一三九名のうち、一〇〇名はすでに死亡した」
報告書は最後に、のこりの三九名の死刑囚をすくう司法上の可能性と、拷問の実行者たちを起訴して裁く必要性を指摘したのち、つぎのような一節でむすんでいる。
「われわれが、これらのアメリカ人が犯した罪を、わが国内でみずから公表しない場合には、アメリカの威信とアメリカの正義は、永久にとりかえしのつかない被害をこうむるであろう。もしも、われわれが率先して罪状を調べあげ、公然と非難し、それをゆるさない立場を表明するならば、われわれにはまだ誤りを部分的につぐなう余地がのこされている。もしも、われわれがそれをためらい、われわれの敵が国外でわれわれの罪状をあばきたてるのを待つだけだとしたら、われわれには頭をさげ、恥じて事実をみとめる道しかのこされていない」
シンプソン陸軍委員会の三人のメンバーの一人だったファン・ローデン判事は、すでに紹介したように、この報告書の内容を一九四九年一月九日づけのワシントン紙『デイリー・ニューズ』および同年同月二三日づけの英紙『サンデー・ピクトリアル』に暴露した。報告書が提出されたのは、その前年の一九四八年だった。新聞紙上での暴露という非常手段に出た理由の一つは、以上の経過からも容易に読みとれる。つまり、「報告書提出以後にも五名の絞首刑」という、のっぴきならない実情が目の前で展開しつづけていたからだ。新聞紙上での暴露は、「ストップ・ザ・ハンギング!」という痛切なさけびだったにちがいない。
ローデン判事が暴露を決意したもう一つの事情は、当のシンプソン陸軍委員会の内部における意見の相違、あるいは対立にあったと思われる。『二〇世紀の大嘘』には、ローデン判事以外の主要メンバーの変節の有様が簡単に紹介されている。そのままにしておいたらローデン判事は少数派となり、調査報告は「極秘」あつかいで数十年も埋もれてしまったのかもしれない。
アメリカの議事録を調べてみると、二つの新聞記事がでた直後の一九四九年一月二七日に、上院で大統領にたいする短い質問があり、副大統領が答弁に立って報告書の要約の議事録への記載をみとめている。以後、同年二月八日、七月二六日と、次第に長時間の議員側の意見陳述があり、報告書の全文公開がなされたという経過である。
だが、「拷問の実行者たちを起訴して裁く」だけで、本当の解決がえられたのだろうか。
ニュルンベルグ裁判も東京裁判も、特殊で一時的な戦争終結作業の一環であった。国際法上の明文規定はない。だが、裁判という形式を主張した以上、すくなくとも純理論的な意味では、本来の裁判における「上訴」「上告」「差し戻し」「再審」といった手続きの必要性を否定しさることは不可能であろう。判決の重要な要素となった被告の「自白」が、拷問という不法行為によって獲得されたものであることが判明した以上、本来の裁判ならば、審理をやり直さなければならないはずなのだ。
シンプソン陸軍委員会の調査は、アメリカ軍がダッハウ元収容所の裁判でおこなった拷問についてのものであるが、ニュルンベルグ裁判の主要法廷であった国際軍事裁判および、その後の関連裁判についても、同様の問題点を指摘しないわけにはいかない。
そこで本書を仮に、きたるべき「再審」請求への準備作業として位置づけてみよう。
そのさいの仮定的な「再審」で決定的な重要性を持つのが、「新証拠」ともいうべき「チクロンB」と「ガス室」についての「科学的かつ法医学的な調査結果」である。
この「新証拠」は、裁判の用語でいえば「物証」である。これまでは「被告の自白」や「生き証人」の「証言」という「人証」が絶対視されてきた観がある。すでにのべたような「生き証人」インタヴューの必要性についての議論も、この延長線上にある。
ここではまず最初に裁判所の制度上の、高裁とか最高裁の例をとって考えてみよう。
最高裁のことを悪口で「最低裁」と呼ぶ法律家もいる。だから、高裁とか最高裁とかに例をとるのは、決して中身が優れているという意味ではない。あくまでも制度上の位置づけである。
上級裁判所といわれる高裁や最高裁は、下級裁判所の判決をくつがえしたり、「差し戻し」や「再審」の決定をくだすことができるが、そのさい、「事実審理」といわれる作業を法廷でくりかえさなくてもよい。高裁や最高裁も法廷での「事実審理」や現場検証はできる。だが、制度上は、「事実審理」は下級裁判所が一応おこなっているというのが建て前だから、下級裁判所から送られてきた記録の書類審査だけで判決をくだすことができるのである。「事実審理」、またはその一種としての「証人調べ」の義務はない。単に「手続きのあやまり」を発見しただけでも原判決は破棄できる。最高裁は原判決を破棄する場合には「口頭弁論」を開く習慣だが、わたし自身が傍聴した例では、まったくの形式的手続きでしかなかった。
「ホロコースト」見直し論の場合にも、すでにニュルンベルグ裁判以来の一連の「ホロコースト裁判や、数多い著述を前提にして、その不合理性を指摘しているのだから、あらためて直接的な「証人調べ」のやり直しを絶対視する必要はないのである。
むしろ重要なのは、すでに何度も指摘したような、「新証拠」に相当する「チクロンB」と「ガス室」の科学的調査の、理論的な位置づけ方である。
この場合、従来の判決の最大の根拠となっていた「証言」または「人証」と、「新証拠」の「物証」とは、どちらかが成り立てば「有罪」という関係ではない。「物証」のあたらしい発見、または再検討にもとづく論証が正しいとなれば、「ガス室」の存在と、「ガス室」による大量虐殺を主張してきた「証言」の方は、足元からくずれ、まったく成立しなくなるのである。
「新証拠」または証拠の再検討が、それ以前の判決を完全にくつがえした例はおおい。戦後日本の一連の謀略事件のなかから、被告が最終的に無罪になった典型的事例を紹介しておこう。
松川事件では、被告が列車を転覆させる目的で線路のレールを外したとされていた。検察側は、その証拠として、線路のレールを外すのに使ったと称する「バール」を提出していた。警察が被告の仕事場で発見したというのだ。ところが、実験してみると、この「バール」では線路のレールを留めている犬釘を外すことはできなかった。
白鳥事件では、被告が白鳥刑事を殺害する目的で「集団謀議」をおこない、実弾の射撃訓練をしたとされていた。検察側は、その証拠として、峠の土のなかから掘りだしたと称する「銃弾」を提出していた。ところが、この「銃弾」には、長期間土のなかに埋もれていた場合には、かならず発生しているはずの「腐食応力割れ」という現象が見られなかった。
菅生事件では、被告が交番を爆破したとされ、「目撃証人」の警察官は「シュルシュル」という音で導火線が燃えているのに気づいたと証言していた。ところが、「シュルシュル」という音は、映画で工夫された効果音にすぎなかった。本物の導火線は音を立てずに燃えるのだった。
「ホロコースト」見直し論者は、現在、「チクロンB」と「ガス室」の科学的調査を、このような決定的かつ核心的な「新証拠」ではないかという意味で提出している。この「新証拠」を根拠にして、裁判なら「再審」に相当する「見直し」をおこなえと要求しているわけである。裁判の法廷としてもすでに、カナダのツンデル裁判で『ロイヒター報告』が提出されている。その裁判の結果と意義については、のちに紹介するが、最高裁は「ホロコースト」についての判断を避けながらも、「虚偽の報道」に関する罪に問われていたツンデルを「無罪」と判断した。
「生き証人」の「証言」や被告の「自白」などの「人証」の証拠価値の再検討の方は、むしろ、「新証拠」の評価をさだめたのちに、この「物証」と照らし合わせながらの共同作業として、あらためて大規模に展開されるべきなのではないだろうか。
第5章:未解明だった「チクロンB」と「ガス室」の関係
(41)「ユダヤ人は自然死」の意見は紹介するが「チフス」を無視へ