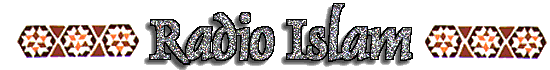ユダヤ民族3000年の悲劇の歴史を真に解決させるために
電網木村書店 Web無料公開 2000.9.9
第4部 マスメディア報道の裏側
第8章:テロも辞さないシオニスト・ネットワーク 1
シオニスト・テロ・ネットワークの「歴史見直し研究所」襲撃
以下の文章のほとんどは、『マルコ』廃刊事件以前に仕上げていたものである。むしろ、そのままの方が意味があると思うので、あえて手を加えない。
さて、最後に予測しておかなければならないのは、本書のテーマである「ホロコースト」の見直し論が、今後、日本国内で遭遇するであろう障害、妨害である。
その予測の材料として、まずは国際的な歴史的事実を紹介しよう。
さきに紹介したNHK放映の『ユダヤ人虐殺を否定する人々』では、カリフォルニアにある「歴史の見直し研究所」(IHR)を「ナチズム擁護派の一つの拠点」として位置づけていた。だが、この研究所の活動内容は、その名のとおりの「歴史の見直し」であって、決して「ホロコースト」の見直しだけを目的にしているわけではない。案内のパンフレットも手元にあるが、刊行図書の案内を見ると、日本軍が真珠湾を攻撃するにいたる経過の研究など、非常に多彩である。決して一定の政党や思想団体に従属する組織ではない。だから、協力する学者や文化人の思想傾向もはばひろいようだ。
しかも、IHRについては、先の映像作品がまったくふれようとしなかった重要な事実がある。IHRの事務所に爆弾をなげこむ焼き打ちなどの白昼テロ行為が、再三にわたっておこなわれていたのだ。いやがらせの街頭デモなどの前後の状況から判断すると、犯人はあきらかに、いわゆるユダヤ人のシオニスト過激派である可能性がたかい。
IHRは一九七八年に設立されたが、すぐにシオニスト組織のしつような攻撃の対象となった。
IHR発行の「特別報告」、『シオニスト・テロ・ネットワーク』によると、いやがらせの街頭デモにはじまる公然として攻撃が、まずあった。さまざまな非合法の攻撃手段のなかでは、車の破壊などは序の口で、タイヤに穴をあけられたのが二二回、数えきれないほどの事務所や夜間の自宅へのいやがらせ電話、事務所への銃撃、放火、三度の爆弾なげこみなどがあった。事務所への攻撃の方法は、火炎ビンから爆弾まで、次第に強力な攻撃となり、一九八四年には、貴重な資料がすべて灰になった。そのさいの損害は金額にして四〇万ドル(約四億円)に達した。
しかし、これらの襲撃についてメディアはこぞって何らの報道をもしようとせず、警察当局は犯人捜査の努力を放棄した。これが世界中に「民主主義」を押し売りしているアメリカの、本国における言論の自由の現実なのである。
『シオニスト・テロ・ネットワーク』にもでてくるが、もっとも戦闘的なシオニストの組織に「ユダヤ防衛連盟」(JDL)がある。JDLの危険な実態を徹底的に暴露した『ユダヤを剥ぐ/武装テロ組織JDLの内幕』の著者、ロバート・I・フリードマンは、アメリカ国籍のユダヤ人で反シオニストのジャーナリストである。
暗殺、放火、爆弾なげこみの背後にはイスラエル政府機関?
シオニスト過激派の活動を正確に認識するためには、イスラエル建国を推進したシオニストが、政治集団であると同時に、世界に比類のない強力なテロリスト集団でもあったという、厳然たる歴史的事実を、あらためて確認する必要がある。
名前が知れわたっているテロリストのなかには、なんと、首相にまで成り上がったメナヘム・ベギン、イツハック・シャミルらがいる。かれらのテロの対象は、パレスチナ地方のアラブ人だけではなかった。イギリス当局は、アラブ側の抗議にしぶしぶこたえる形で、委任統治下にあったパレスチナへのユダヤ人の移住を制限したりしていた。だから、シオニストのテロ集団は、イギリス当局にたいして何度もテロ攻撃をおこなっていた。攻撃の口実は、ユダヤ人に「ナショナル・ホーム」を約束した一九一七年の「バルフォア書簡」の早期実現要求であった。「イギリスが約束を裏切っている」からテロは当然だというのが、かれらの論理だった。
「バルフォア書簡」を「バルフォア宣言」などと表現して、いかにもイギリスが公式の約束をしたように論ずる学会の習慣がある。だがこれはあくまでも、植民相のバルフォアが金融財閥の当主、ロスチャイルドにだした非公式の「手紙」にすぎないのである。
公式の国家間条約でさえ、議会で批准されなければ発効しないのが国際常識である。しかも、イギリスがパレスチナを支配していたのは、国際連盟の委任統治という名目によってだった。その名目からしても、国際連盟の承認もなしに勝手な処理がゆるされるべきではない。ましてや、アラブ人などの現地の住民の立場からすれば、イギリスにはなんらの権利もないのである。それなのに、アラブ人にもイギリス人にもテロ攻撃をくわえて、強引にパレスチナ分割決議をうばいとったシオニストとユダヤ系財閥と、それをバックアップしたアメリカの行為は、決してゆるされてよいものではない。
かれらのテロによる何十人ものイギリス人犠牲者のトップクラスには、イギリス本国の植民相、モイン卿がいた。かれは殺される直前に、「ユダヤ人の天国としてはマダガスカルが適当」と口走っていた。ヒトラー時代のマダガスカル案には沈黙をまもったシオニストが、情勢がかわると、おなじ案を口にしただけで暗殺という手段にうったえるようになったのである。さきに紹介した元首相のイツハック・シャミルは、モイン卿の暗殺を実行した「シュテルン部隊」の最高指揮官だった。
イスラエル建国を可能にした必須条件、パレスチナ分割決議をうばいとるさいにもテロが決定的な役割をはたした。アラブ諸国の強い反対の意思表明を前にして、アメリカのトルーマン大統領もイスラエルの建国に反対する。シオニスト世界機構議長のヴァイツマンも、ほとんどあきらめかけていた。ラカーは、『ユダヤ人問題とシオニズムの歴史』のなかで、その間の事情をつぎのようにしるしている。
「エルサレムでは、協議が割れていた。ワイズマンは、シオニスト小評議会の会合で、ユダヤ人国家を要求したことはおそらく間違いであったと述べた。
『我々はいつも無理押ししようとしている』
しかし優位を占めたのは行動主義者だった。一九四六年六月一六日には、またハガナの大規模な行動があり、九つの橋が爆破され(ヨルダン河に架かるアレンビー橋も含まれた)、ハイファの鉄道作業所が被害を受けた。イギリス人は六月二九日、パレスチナのシオニスト執行部の構成員や、その他多くの著名人の逮捕を命令することにより報復した。ユダヤ機関事務所は閉鎖され、公的な建物や入植地は捜索を受けた。
イギリスとシオニストの関係は、イルグン[シオニストの軍事組織]がエルサレムのキング・デーヴィッド・ホテルを爆破した時、最も低調なものになろうとしていた。この爆破により、イギリス人、ユダヤ人、アラブ人合わせてほぼ一〇〇人の人命が失われた」
さきに紹介した元首相のメナヘム・ベギン、イツハック・シャミルらは、この引用文中の「イルグン」のメンバーだった。テロによって「国盗り」を果たし、テロリストを首相にいただくイスラエルにとって、テロはもはや、国益を守るための宿命の観さえある。
一九七八年には、「ホロコースト」見直し論者で『六〇〇万人は本当に死んだか』を普及していたフランス人の歴史学者、フランソワ・デュプラが暗殺された。フランスの代表的な保守系新聞『ル・モンド』などでも何度か報道された事件である。デュプラが運転していた車が爆弾でふっとび、本人は死に、同乗していた彼の妻も両足をうしなった。直後に、ユダヤ人のアウシュヴィッツ関係組織、「記念コマンド」と「ユダヤ人革命グループ」が、みずからの犯行だとなのりをあげた。
IHRが設立されたのは、デュプラが暗殺された年の一九七八年である。『シオニスト・テロ・ネットワーク』では、デュプラ暗殺事件の技術的背景をつぎのように分析している。
「この襲撃はいかにも洗練されており、どこかの政府機関が関与していないと考えるのは困難である」
「どこかの政府機関」といえば、当時すでに建国三〇年をへていたイスラエルの必殺情報機関、「モサド」以外にはありえない。
『シオニスト・テロ・ネットワーク』の「フランソワ・デュプラ殺害事件」のつぎの項目は、「イスラエル・コネクション」である。この項目では、元モサド機関員の著書を引用しながら、イスラエルが各国の「ユダヤ人防衛グループ」に武器を供給し、自国内で軍事訓練をほどこしていた状況などを解説している。