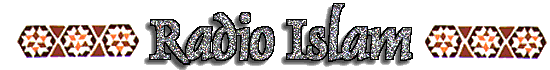ナチス〈ホロコースト〉をめぐる真実とは?
イスラエル建国・パレスチナ占領の根拠は?
電網木村書店 Web無料公開 2000.5.5
訳者解説(その2)
今後の課題は、本書でも力点を置いて指摘されている科学的研究である。以上のような問題点についての報道、研究の自由が保証された上で、アメリカや旧ソ連に押収されたままの膨大な資料の、情報公開を求め、全面的な、しかも大規模な見直しの研究を促進することであろう。
ガロディが何度も強調しているのは、歴史の科学的な研究こそが最良の検事論告となること、つまりは実証的な歴史研究に、極めて実践的な価値があるということである。
ガロディは、レバノン侵略に抗議して以来、様々な妨害に直面しながら、それでもなお諦めることなく、さらには、その根底に潜むイスラエル問題、もしくはパレスチナ問題を真に解決するためにこそ、火の粉を浴びる覚悟で、アメリカの拒否権と一対になったホロコーストのご本尊の欺瞞に迫っているのである。本訳書の三三八頁ではを問うている。平和的な解決の落とし所については、国連パレスチナ分割決議の「適用」(本訳書三二四頁)と記されている。
この決議自体には問題が多い。だが、かつては「地中海に追い落とす」というのがスローガンだったPLOも、事実上の妥協を表明している。冒頭の「訳者はしがき」に記したアラブ人記者は、この解決策の可能性について語った際、悲しみと寛容さを交えた両手の掌を広げる身振りで、こう付け加えていた。
「でも、それには、ありがとうの一言がほしい。それがないのが残念だ」
私自身としては、本書の作業が終り次第、現在も続行中の『歴史見直しジャーナル』の定期発行と並行して、主要な資料の翻訳に集中する予定である。その際、たとえば、本訳書の一七八頁の訳注1でも指摘し、拙著『アウシュヴィッツの争点』でも一部を紹介したアメリカ議会の議事録、ニュルンベルグ裁判の継続としてのアメリカ軍によるダッハウ裁判での「拷問問題」などは、揺るがすことのできない公式記録であろう。
合わせて指摘して置きたいのは、当時の欧米のメディアの報道状況の、実証的研究の必要性である。拙著『アウシュヴィッツの争点』でもすでに記したが、たとえば、アメリカ軍がフランス国境に近いダッハウ集中収容所を解放した当時の『ニューヨークタイムズ』を二か月分だけ見たところ、どこにも「ガス室」の話は載っていない。ソ連軍が三か月も前に解放したアウシュヴィッツ集中収容所に関する短信にも、「ガス室」の話は入っていない。ニュルンベルグ裁判が始まるまでは、誰しもが、「またあの第一次世界大戦の時と同じヨタ話か」と思っていた可能性が高いのである。
私には、こういう研究を、こっそり独占する好みはないし、おそらく一人では不可能に近いと思っているので、読者にも訴えるのである。日本国内でも、国会図書館に行けば、『ニューヨークタイムズ』などのマイクロフィルムを見ることができる。ただし、マイクロフィルムを映写器具で直接見るのは目に悪いので、タイトルで選んで、記事を読むのはコピーを拡大してからにするなどの工夫が必要であろう。
本書の訳文は、すでに冒頭の「訳者はしがき」に記したような事情の下の仕事である。自分なりに全力を尽くしたつもりだが、不十分な点が多々あるに違いない。本訳書の改訂増補の機会は望外ではあるが、いずれ改めるべき点は機会を得て改めるべきなので、諸賢の忌憚ない教示を願う。
なお、本訳書の発表は、巻末資料作成中に発生した『週刊金曜日』との紛争によって、大幅に遅れた。
『週刊金曜日』は、一九九六年一月一八日に発表された花田元『マルコポーロ』編集長の朝日移籍に反発して、同年六月一四日以降、「『朝日』と『文春』のための世界現代史講座」と題する連載を開始した。この状況下、一九九六年一〇月ころからは、投書欄で、本件「ガス室」問題に関連して訳者個人への誹謗中傷的表現が乱発されはじめた。一九九七年一月二四日からは前記連載講座(9)以後、六回にわたる連載記事、「『ガス室はなかった』と唱える日本人に捧げるレクイエム」が現われ、その内の五回は、訳者個人と拙著『アウシュヴィッツの争点』への、ねじくれ曲がった誹謗中傷に終始していた。訳者は、やむをえず、一九九七年四月一八日、株式会社金曜日および執筆者二名を相手取る損害賠償請求訴訟を起こした。九月九日には、逆に、ドイツで当方を刑事告発したという記者会見が日本外国人特派員協会主催で行われた。いくつかの記事になっているが、別途、詳しく批判を加える。
その間、遅滞の事情をフランスのフォーリソンに漏らしたところ、何度かのやり取りを経て、先方の事情が、かなり詳しく伝わってきた。まず、フォーリソン自身が、「ガロディ/アベ・ピエール事件」に関する論評記事を理由として、刑事告発されており、一九九七年九月二五日の午後一杯、被告として法廷で取り調べを受ける。ガロディと出版者のピエール・ギヨームの二人は、一九九八年一月、八、九、一五の三日間の午後一杯、刑事法廷に召喚されることに決まった。
フォーリソンは同時に、インターネットのホームページ記事のコピーを送ってきた。私は、まだパソコンまで手を伸ばす時間の余裕がないので、有志の協力を訴えた。彼のホームページのアドレスは、つぎの通りである。
http://www.abbc.com/aaazgh/engl/ (2018.12.3現在不通)
フォーリソン自身が送ってきたインターネットのホームページ記事コピーには、本書に関わる重大な事件が記されていた。ここでは、その要約だけを記す。
自費出版で改訂増補の本書を扱う「知識文庫」が、一九九六年七月一六日に、「ベタル・コマンド」と名乗る集団に襲撃されていた。「知識文庫」の経営者で、チャウシェスク時代のルーマニアからの政治的亡命者、ジョルジュ・ピスコッチ=ダネスコが負傷し、店が荒らされ、希少本を含む約二〇〇〇冊の本が販売不能の状態になった。被害額は約二五万フラン(一フランが二二円のレートで約五五〇万円)に達するが、保険会社の補償はない。
「ベタル」は、本書の第2章第1節「シオニストによる反ファシズム運動の神話」に登場するシオニスト組織である。ファオーリソンの解説によると、最も過激な極右民族主義者で手段を選ばないテロリスト、ジャボチンスキーが率いる分派の系統である。この分派には、イギリスの植民地担当国務大臣、モイン卿を殺害したシャミール集団も含まれている。シャミールは、湾岸戦争当時のイスラエル首相である。
さらには、右のフォーリソンのアドレスから出発して、インターネット・サーフィングを楽しんだ友人から、つぎの情報がファックス通信で送られてきた。
やはりフランスの見直し論者、ジョルジュ・ティオンのホームページによると、本書の初版本を出したピエール・ギヨームの出版社の社名、La Vieille Taupe[直訳すれば、老いたモグラ]は、『ハムレット』第1幕第5場の台詞に由来するとのこと。英語では old mole。父王が暗殺された秘密を親友ホレーショに打ち明けようとするハムレットは、ホレーショに対して、自分の剣の上に手を置いて秘密を守る誓いをせよと迫る。すると地下から父王の亡霊が「誓え」と呼応する。場所を移すと、そこでもまた、「彼の剣の上で、誓え」という声が響く。これに対してハムレットが、 Well said, old mole! と言うのである。相手が父王の亡霊であることを知っての上での台詞だから、 old には、年長者への敬意と親しみが加わっている。これが歌舞伎ならば、「よくぞ申された。地下の御老君」といったところ。これに続くハムレットの台詞も、A worthy pioneer![さすが先達(穴掘り、工兵の意味あり)!]という評価になっている。
地下に潜みながら、故事と地上の現状に通じ、情勢の変化に即応して、すかざず行動するという意味であれば、歴戦の見直し論出版社には、ピッタリの名称である。
ところで、この出版社について、本書の冒頭「訳者はしがき」で紹介した『世界』(96・9)の記事「パリ通信」では、「かねて戦闘的なネガショニストどもの著書を出してきた本屋」という非難がましい表現をした上で、Vieille Taupeを「老いぼれもぐら」、「しわくちゃ婆さんという意味もある」と説明していた。これでは味も素っ気もない。まずは、そこでもすでに指摘したように、冤罪報道の典型的パターンである。被疑者側からまったく取材をしていないのが明々白々ではなかろうか。
念のために「パリ」ならぬ東京の図書館で、すべての大型の仏和辞典で Taupe を引くと、vieille Taupeについては、必ず「いじわる婆さん」「くそばばあ」などとあるから、良く使われる表現のようである。しかし、どの辞書にも、「しわくちゃ婆さん」の訳例は見当たらない。
はてさて、この件の真相追及は、さして決定的な問題をはらむわけではない。ほんの味付けだが、私自身の訪仏計画の中の楽しみに取って置くことにしたい。
最後に、印刷工程開始の直前、八月二五日発行の『ドレフュス家の一世紀』(平野新介、朝日新聞社)を入手した。参考になる点は多々あるが、本文中の「カルパントラ事件」に関係する部分についてのみ、一言しておきたい。
南フランスの小都市カルパントラには、ドレフュス事件の主人公、アルフレッド・ドレフュスの姉が嫁いだ一家がある。著者の平野は現地を訪れており、「ネオナチの墓荒し事件」という項目を立てている。
概略を先に記すと、一九九六年夏、つまり本書の底本となる改訂版発行以後、「五人のスキンヘッド」の一人で、「アヴィニョンの総合情報局に出頭したヤニック・ガルニエという男が、ついに自供した」ことによって、「事件がやっと決着した」というのである。
ところがまず、自供の内容には、「ジェルモンの遺体には、持参のパラソルでくし刺しを試みた」とある。本訳書三〇一頁から三〇二頁にあるように、「串刺しにはされていなかったことを、捜査官が確認した」のであれば、この自供は嘘である。つぎに、「なるべく証拠を残さぬように、スプレーでの落書きも自制した」という自供は、「世間をあっと言わせるような、どえらいことをやろう」という動機と矛盾するし、スキンヘッドらしからぬ振る舞い方である。しかも、「首領格のゴメスは、事件から三年後に交通事故で死んで」いる。
さらに平野は、「自供した」ことのみを根拠にして「事件がやっと決着した」としている。しかし、形式的にもせよ、一応の司法的「決着」とは、検察当局が自供を含めて犯罪全体の証拠を吟味した後に、被疑者を起訴し、裁判所で判決が下されることでなければならない。残念ながら、その点の記述がない。ガルニエが別件で逮捕され、取引に応じたという可能性もある。この問題には追跡調査の必要がある。