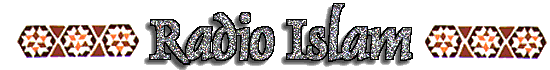ナチス〈ホロコースト〉をめぐる真実とは?
イスラエル建国・パレスチナ占領の根拠は?
電網木村書店 Web無料公開 2000.1.7
訳者はしがき4・著者の宣言・著者と訳者の略歴
4.文献・凡例・訳語・訳題の主旨説明
引用文献の取り扱い方については本書の「結論」の項、三二七頁に、著者の考え方が、つぎのように示されている。
「多くの読者は、結論に到達するのを非常に急ぎ、しばしば、無味乾燥な証拠を挙げる作業を嫌うものである。しかし[中略]、私は、読者には余分な手間となり、疲労の原因となることを意識しつつも、あえて、いかなる問題をも、その出典を明らかにせずには提出しなかった」
つまり、本書の場合、著者の引用方法それ自体が、裁判の法廷における証拠吟味の仕方と同様になっている。原著では、すべての引用資料の頁数が記されていたりして、一般には注釈のない小説の方が好きな読者には、一番嫌われる構成になっている。この訳書の本文では、読み易さを重視して、ほとんどの場合、題名と発表年度に限り、本文と直接関係する場合のみ執筆者名を記すに止めた。特に原典に当たりたい方向けには、資料説明の残りを巻末にまとめた。さらに、原著にはない「人名索引」と「事項索引」「資料索引」を作成し、研究者の便宜を図った。しかし、論旨を理解する上では、いちいち巻末を見なくても不都合はないと思う。
さて、以上のような著者の力点の置き方もあり、本書における資料の選択と問題点の解明の仕方は、第一級である。自費出版の改訂版という事情を反映してか、記述が重複したり、同じ材料が何度か出てくる場合もあるが、それぞれの段階に応じての、いわゆる螺旋状の上昇とも言えるし、前後関係を良く吟味していただければ、この複雑な事件の立体的な各側面に、つぎつぎと新たな角度からの照明が当てられていることが、お分かりになるだろう。
なお、先にも記したが、本書では、すでに各所で議論されている通り[Nations Unies]を、字義通りに「連合国」と訳出する。「国際」(International)という単語はまったくないし、戦争中の組織名の引継ぎだという面を明確にしておく必要がある。
「連合国」の本質を分かりやすく言えば、日本の江戸時代の「関八州」の大親分に当たるのが、「世界五州」の大親分、アメリカである。アメリカ以外に「拒否権」という手前勝手な特権を持つ中親分は、イギリス、フランス、ソ連(現ロシア)、中国であるが、この内、「西側」とされてきたのは、イギリス、フランスだけであり、この両国には、国力の相対的な低下もさることながら、第二次世界大戦でアメリカに助けられた弱味がある。つまり、西側世論を「連合国」の決定で押さえ込む場合に、アメリカの言論を操作する作業の位置付けは決定的なのである。こういう力関係の構図を通して見ると、パレスチナ分割決議は、まさに、大、中、小の「世界五州」親分衆による領土切り取り談合でしかない。本書では、この点、シオニスト・ロビーが果たしてきた歴史的な役割を、実に適格な実例にもとづいて解明している。
「nation」は、国民、国家、民族を意味する曖昧な言葉である。特にシオニズムの場合には、「民族」は誤訳に近いと判断し、「国民」または「国家」とし、「peuple」の方を「民」「民族」「人々」とした。「nationalisme」は「国家主義」とした。イスラエル国家などの場合の国家は、「Etat」である。
もう一つ、これまでの慣行に逆らう独自の訳にこだわったのは、つぎの「著者はしがき」にもすぐ出てくる「バルファオ意思表示(declaration)」である。一般には「宣言」と訳されているが、日本語、もしくは漢語の「宣言」では、いかにも公式の感じが強い。拙著『アウシュヴィッツの争点』では、もともとはロスチャイルドへの個人的な手紙の内容であり、条約でも外交上の覚書きでもないことなどを指摘し、むしろ、無責任な裏取引のニュアンスを強調するために、あえて「書簡」と記したが、今度は原文があるので、そうもいかない。そこで、「意思表示」としたのである。
ナチス・ドイツの「集中収容所」は原語の直訳である。
「強制収容所」とか、ましてや「絶滅収容所」などという別名または恣意的な造語で歴史を論ずると、最初から先入観念にとらわれ、真相が見抜けなくなる。たとえば、本書にも出てくる『イェルサレムのアイヒマン』の著者、ハンナ・アーレントは、まだホロコーストを認める立場だが、イスラエルの建国指導者たちの多くが、収容所への移送や、その後の管理についてナチと協力した「ユダヤ人評議会」のメンバーだった事実を明らかにした。そのために、シオニスト・ロビーから袋叩きの目に遭っている。こういう言論状況のままでは、まともな議論はできない。事実を虚心坦懐に見るためには、用語の方も、原意通りに素直に表現する必要がある。事実は「移送」であり、断じて「絶滅」ではなかった。だから、「ユダヤ人評議会」の指導者たちは、ナチと協力したのである。いかな政治的シオニストといえども、「絶滅」に協力するほど残虐でも、愚かでもなかったのである。
旧約、新約の聖書の字句は、基本的に日本聖書協会訳により、原著と文章の切り方が違う場合と、単語の訳のニュアンスが前後の文脈と合わない場合のみ、拙訳とした。
原文で斜字、大文字の強調は、引用文、書名、論文、作品名の場合、『 』「 」内に普通の文字で記し、本文中の単語の場合はゴシック文字とした。原文および引用文中の( )内の単語または文章は、特にカッコに入れることに意味がある場合を除き、カッコを外して読みやすくした。短い訳注と訳者が付けた小見出しは[ ]内に記した。
固有名詞のカタカナ表記は、発音記号をも兼ねてしまうので、日本語訳の最大の難所となっているようだが、訳者の持論のラディオとヴァ行以外は、特にこだわらず、おおむね慣用と前例に従った。たとえば旧約聖書に関しては慣用に従って「モーゼ」と記し、現代人の名前の場合には「モシェ」とした。ドイツではニュルンベルクと語尾が澄む発音を、慣用の濁ったアメリカ訛りでニュルンベルグのままとしたり、逆にアメリカ人で英語訛りではリュウヒターとなっている人名を、前例のドイツ語訛りでロイヒターにした。
慣用が定着していない場合には、現地のお国訛りに近寄せるように努力した。ドイツ語源でも、本人がイギリスやアメリカに定住していることが判明している場合には、英語訛りとし、ドイツ語型で所在が明確でない場合は、ドイツ語の標準訛りで表記した。訳者の認識不足のために不適切なカタカナ表記になっている場合には、お許し願いたい。
念のための補助として、原文のローマ字表記を巻末索引に記したが、固有名詞の表記はフランス式で原語と綴りが違う場合がある。これも、ヨーロッパ文明の中心的存在を自負するフランス人が、他国の綴りや発音を特に尊重していない証拠の一つである。
イギリスの英語学の本には「スペリング・ポロナンシエイション」(綴り発音)という項目があり、外国人が地名を綴り通りに発音するので、現地の住民も、それに習うようになったという例が記されている。訳者の考えでは、発音通りに表記しない方が悪いのであって、日本人の場合、特にぎこちなく衒学的にこだわるのは、欧米コンプレックス以外の何ものでもない。仲間内の悪口の種にして足を引っ張るとなれば、さらに下の下の俗物、似非学者根性である。
ヘブライ語、および宗教関係の訳語に関しては、湾岸戦争以来旧知の「パレスチナに平和を京都の会」代表、諸留能興の協力を得た。それでも分からない部分については、著者のガロディと旧知のフォーリソンにも問い合わせた。他にも多くの友人知人に教えを受けたが、本書の性質上、特に氏名は記さずに感謝の意を表明する。
本書の原題を厳密に訳すと『イスラエルの政策の基礎をなす(または、支える)諸神話』であろうが、これはいかにも長いし、くどくなる。さらに本書の内容に立ち入ると、このすぐあとの「著者はしがき」にも、イスラエルは「世界の暫定的な主人、アメリカ」のための「不沈空母」という位置付けが出てくる。イスラエルが欧米列強にとっての「満州国」という認識は、大声で語られないだけの話であって、まともな議論では常識中の常識である。そこで、満州国に対する中国側の呼び名、「偽満」を真似し、訳題の『偽イスラエル政治神話』を選んだ。
かつての日本の「満蒙開拓」でも、源義経がジンギスカンになったなどという稚拙な現代神話が現われた。古今東西、違法不当な侵略は偽物の神話を必要とするのである。
ところで、この「はしがき」の最後に、一言だけでも指摘しておくべきだと思うのは、本件に関する主張を「自由主義史観」と同等に扱う向きの存在である。その一部とは議論をしたこともあるが、まずは、拙著『アウシュヴィッツの争点』の存在を知っていても読まずに、先入観念に従って判断し、感情的に反発しているだけだった。そのことだけで見ても、事実に基づいて歴史を見直すという基本的姿勢を欠いている。
「自由主義史観」そのものは、お粗末極まりないデマゴギーなのだが、それに反対の立場を表明しているからといって、それだけで科学的な歴史観に立つ必要十分条件を満たしていることにはなり得ない。五十歩百歩のミーハー的お粗末さであり、これも論外なのだが、詳しくは稿を改めて論じたい。
[本訳書の底本となった改訂版の表紙の裏に囲みで記された著者の宣言]
私は、半世紀以上にわたって、フランスの最大手の出版社から諸々の自著を発表し続けてきたが、その挙げ句の果てに、現在、このシオニストの邪教に関する論集をサミスダット[訳注]により、自費出版することを余儀なくされている。
それというのも私が一九八二年以来、イスラエルの政策への批判というタブーを破りを続けてきたからである。イスラエルの政策は、その後の一九九〇年七月一三日に制定された悪辣なゲーソ=ファビウス法によって、さらに強い庇護を受けるようになった。この悪法の出現は、懲罰的な法制の助けによって論争を回避へと追い込んだ第二帝国の“言論取締法”の現代フランスへの復古にほかならない。
以上の理由により、仕事の継続を望む出版社は、“思想の統一”と知的テロが、その国……フランスではなかったのだが……を支配したチャウシェスク時代と同様に、このサミスダット出版物の委託販売を引き受けてくれた知識文庫とパリのルーマニア文庫を通して、注文を受けるほかないのである。
R.G.[ロジェ・ガロディ]
訳注:ロシア語で「自費出版」だが一般には「地下出版」と訳されている.
[奥付の著者、訳者、略歴紹介]
ソルボンヌに学び、20歳で共産党に加盟。ナチスドイツ占領下でレジスタンスに参加、逮捕、収容所暮らしを経験。1956~1968年には共産党政治局員としてイデオロギー部門を担当したが、ソ連は社会主義ではないと主張し始めた結果、1970年に除名。哲学者として日本でも広く知られ、『認識論』『自由』(青木書店)『二〇世紀のマルクス主義』(紀伊国屋書店)『人間の言葉』(新潮社)『カフカ』(思潮社)などの訳書がある。
防衛大学校(3期生)中退、東京大学文学部卒。1961年・日本テレビ放送網入社、労組役員、解雇反対闘争などを経て著述業。『電波メディアの神話』(緑風出版)『読売新聞・歴史検証』などメディア関係の著書多数。本書と関係が深い近著に『湾岸報道に偽りあり』(汐文社)『国際利権を狙うPKO』(緑風出版)『アウシュヴィッツの争点』(リベルタ出版)がある。
追記:以下の囲み文章はWEB公開当時の本文前の付記。2018.11.28下部に移動。