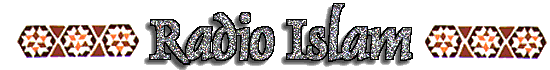ナチス〈ホロコースト〉をめぐる真実とは?
イスラエル建国・パレスチナ占領の根拠は?
電網木村書店 Web無料公開 2000.1.7
訳者はしがき-3.
3.本書は激しい論争の書
本書は、論争的なだけでなく、裁判でやり取りされる書面を思わせる構成になっている。なぜかといえば、著者のロジェ・ガロディは、本書の発表から数えて一四年前に当たる一九八二年以後、基本的には同じ問題で、長期にわたる裁判を経験していた。本書は、その継続としての性格を担っているのである。
レバノン戦争批判で破棄院までの連続勝利判決
一九八二年は、本書にも何度か出てくるレバノン戦争勃発の年である。著者は、友人たちとともに、フランスの言論界の顔のような名門日刊紙、『ル・モンド』に、一面広告記事を載せた。記事の題は、「レバノンでの虐殺とイスラエルの侵略が意味するもの」であった。ところが、この記事の内容を理由にして、著者らばかりか、意見広告掲載を承諾した当時の『ル・モンド』の編集長までが、シオニスト支配下の組織から「反ユダヤ主義宣伝」の名目で告発を受け、裁判所の刑事法廷に召喚されたのである。裁判そのものに関しては、著者らが、日本の最高裁に当たる破棄院に至るまで連戦連勝だった。だが、この事件を契機として、著者は、フランスの大手メディアから排除されるようになった。当時の編集長も『ル・モンド』を追われた。
その間の事情については、この日本語版でも、原著の場合と同様に、表紙裏[このWeb公開では4.の末尾]に著書自身の抗議声明を囲みで入れたが、そこに簡潔に記されている。本文には、さらに詳しい記述がある。
言論弾圧・ゲーソ=ファビウス法との対決
この意見広告事件は、広い意味で言うと、破棄院での勝利判決で終了したわけではなかった。司法界で敗北を喫したものの、シオニスト組織は、あきらめを知らない性格である。または、イスラエルをめぐる中東情勢が落ち着く見込みのない現状では、彼らが振り上げた拳を下ろす場所もない。そこで彼らは政治を動かした。その結果、これも囲み入りの声明に要約されているように、ゲーソ=ファビウス法によって言論法が一部改正され、ニュルンベルグ裁判での決定を否定する言動が、刑罰で取り締まられるようになったのである。
本書は、この「悪辣な法」の存在を承知の上での正面からの挑戦状である。当然、従前と同じ力関係が働き、著者は告発され、今度は法的に本書の初版の出版が阻止され、一般の流通機構から排除された。この訳書の底本は、その後に、実質的な発売禁止の実情をも書き加えた改訂版である。
一部には、ゲーソ=ファビウス法の見直しという観測も報道されているが、現状のままであれば、著者は再び、刑事法廷に召喚されざるを得ない。その際には、本書そのものの内容が、裁判の陳述、書面、法廷外での宣伝などの基本となるであろう。
刑事罰強化の動きに「脆さ」を見る
ゲーソ=ファビウス法の制定への動きには、フランスの国内事情だけではなくて、欧米全体を覆う時代背景がある。
この動きに対するガロディの考え方は、つぎのような本訳書三三七頁の記述に明確に示されている。
「ニュルンベルグ裁判記録を“聖典承認”しようとする彼らの動きは、かえって、その理論的基礎の脆さをあらわにしている」
つまり、逆に言うと、「理論的基礎の脆さ」があらわになってきたからこそ、権力は慌てふためき、刑事罰を強化して議論を取り締まろうとしているのである。しかも、その動きが、最近になって、さらに慌ただしいのである。それは、なぜだろうか。
具体的に、法制定、または刑罰の強化の時期を比較してみると、ほんの最近のことなのである。
●一九九〇年・フランス「ゲーソ=ファビウス法」制定。
[内容……本訳書一四三頁から要約。ニュルンベルグで「決定された人道に対する犯罪」を「否定した者」を「一か月から一か年の禁固、および二千から三十万フランの罰金、またはこの二つの刑の内の一つのみ」によって処罰]
●一九九二年・オーストリア「ナチス禁止法」への追加。量刑は下限を軽減。
[内容……「『アウシュヴィッツの嘘』に対する各国の刑事立法について」(楠本孝『法学セミナー』97.10)から要約。印刷物、放送若しくはその他のメディアにおいて、又はその他公然と多くの人々に見聞に供する方法によって、ナチスの民族謀殺又はその他のナチスの人道に対する罪を事実でないと否定し、著しく矮小化し、是認し又は正当化しようとした者も第3条gによって処罰される。ただし、「第3条g」の量刑は「五年以上一〇年以下の自由刑」から「一年以上一〇年以下の自由刑」に変更]
●一九九四年・ドイツ「犯罪対策法」に「民衆煽動罪」を処罰する一三〇条三項を新設。従来適用されていた「侮辱罪」などの刑法よりも量刑を強化。
[内容……出典は同右。公然と又は集会において、公共の平穏を害するのに適した方法により、ナチスの支配下に行われた刑法二二〇条a(民族謀殺)一項において規定する態様の行為を、是認し、事実でないと否定し、矮小化した者は、五年以下の自由刑又は罰金刑に処す]
つまり、一九九〇年代に入ってから、一斉に、フランス・オーストリア・ドイツという、いわばナチ政権の最初の支配圏で、ニュルンベルグ裁判記録の“聖典承認”の動きが始まったのである。その理由が、ガロディの指摘する通りの「理論的基礎の脆さ」の表われであるとすれば、その最大のきっかけは、一体何だっただろうか。
シオニズムとイスラエルにとって、世界中で一番重要な親代わりの保護国は、アメリカである。アメリカの憲法は、少なくとも法文上、言論の自由についての最新の到達点を示している。法律上の禁圧は不可能である。しかし、本書にも、「アメリカのイスラエル=シオニスト・ロビー」と題する節がある。シオニスト・ロビーが大手メディアを支配しているために、アメリカでも、本件についての発言の自由は、実際には非常に乏しい。
ところが、アメリカの隣国、同じ英語の印刷物と放送が自由に国境を越えるために、文化摩擦さえ生ずる関係のカナダのイギリス系の州の州都、オンタリオで、本訳書一四五頁以下で本書の出典に頻繁に登場するツンデルの「トロント裁判」が行われていた。ガロディは「トロント裁判記録」に対して、「すべての誠実な歴史家にとっての格好の情報源」という評価を与えている。
トロント裁判をめぐる前後の事情については、いずれ、ニュルンベルグ裁判とその後の裁判全体の歴史的経過をまとめて、その中に位置付けたいと考えている。とりあえず、ここでは、以下、簡略に事件の経過を紹介する。
トロント裁判と「ガス室」の法医学鑑定
ツンデルは一九三九年生まれのドイツ系カナダ人である。トロントは、アメリカとの国境をなすオンタリオ湖に面している。オンタリオ湖には、南のアメリカ側から大瀑布で有名なナイヤガラ川が流れ込んでいる。
●一九八五年・トロント地裁の一審でツンデルは、『六百万人は本当に死んだか?』と題する32頁のパンフレットを頒布したことが「虚偽と知りながらの報道により公益を損なう」ことを違法とする刑法により有罪とされ、一五か月の禁固刑の判決を宣告された。
●一九八七年・トロント控訴院(日本の高裁に相当)は、トロント地裁の判事による証拠採用や、陪審員への指示などが違法だと判定し、州政府は再審を命令した。
●一九八八年・トロント地裁の再審で、フォーリソンを中心とする見直し論者による国際的な支援活動が展開された。
この支援活動の最大の成果が、本訳書一九八頁以下に出てくる『ロイヒター報告』である。一言でいうと、「ガス室」と称されてきた施設や残骸には、殺人工場としての機能がなく、殺人に使われたと判定されていたシアン化水素(気体に青酸ガスの別名)の痕跡も認められないという現地調査報告である。ツンデル側は、この報告を、普通の殺人事件で必ず行われる「法医学鑑定」として、法廷に提出した。
実は、『マルコポーロ』廃刊事件の記事最大の目玉も、この報告だった。本件から政治的背景を取り払えば、大量殺人事件である。大量であろうと一人であろうと、殺人は、凶器がなければ成立しない。手で首を締めたりする例もあるが、その場合は、人間自体が凶器である。本件の場合、「ガス室」で「チクロンB」というシアン化水素を発生する殺虫剤を転用したと判定され、そう主張され続けている。だから、その主張が覆れば、それだけで「シロ」となる。こんな簡単なことなのに、『マルコポーロ』廃刊に関する大手メディア報道の中で、『ロイヒター報告』を論じた事例は皆無だった。
●一九八八年・トロント地裁の再審判決でも、ツンデルは負け、九か月の禁固刑を宣告された。しかし、……
●一九九二年・カナダ最高裁は、有罪判決を破棄した。四対三のきわどい過半数であるが、要約すると、トロント地裁の有罪判決の根拠となる法律そのものが、「結果的に少数意見を圧迫しており、カナダの権利憲章に規定された言論の自由を侵害しているので違法」という判決である。問題のパンフレットや『ロイヒター報告』についての判断は避けているが、「見直し論」の立場からいえば、決定的な勝利である。
●一九八八年以降・『ロイヒター報告』は欧米各国で流布され、関係者がドイツ国内に講演会に招かれたりした。ことの性質上、ネオナチもこれを便乗的に利用したので、それをもっけの幸いとして、権力は言論統制を強化した。この手口は、日本の警察が極左暴力集団を泳がせて、弾圧立法の強化に利用したのと同工異曲である。こんな手口すら見抜けないような自称「平和主義者」には、逆に、気をつけた方が良い。免罪符欲しさの自己満足的な運動に無料奉仕させられて、馬鹿を見ただけという話は、そこら中にころがっている。
イスラエルの国策映画『ショア』の欺瞞
さて、日本では、以上の国際的な経過を無視した時代遅れの運動が、もう一つ続いている。
『マルコポーロ』廃刊事件は、『ショア』の日本上映運動と同時発生した。偶然のようだが、戦後五〇年という時代背景から考えれば必然だったのかもしれない。この映画の影響も、本件の日本国内における今後の議論の上で、無視できないであろう。拙著『アウシュヴィッツの争点』でも、一四六~一五〇頁で、問題点の一部を指摘しておいた。
●一九七四年・製作開始、一九八五年・完成の『ショア』には、当然のことながら、ロイヒター報告の影響は、まったく現われない。つまり、時代遅れも甚だしいのである。
これまた、私自身、『ショア』の観客の一部から感情的に反発された体験がある。だが、何人かと話してみて、すでに『マルコポーロ』に掲載されていたロイヒター報告どころか、この映画の製作意図や、監督のランズマンの経歴や思想についても、何も知らず、しかも、知ろうともしない人が多いにのは、今更ながら唖然とせざるを得なかった。
まずは、ランズマンがイスラエル支持のユダヤ人であり、イスラエルの存在を擁護する目的で映画を作ったのだという、最も核心的な情報が、まるで伝えられていない。
私が最初に『ショア』を見たのは、一九九五年一月二八日の土曜日、忘れもしない『マルコポーロ』廃刊決定発表の直前、しかも、その後に訴訟の相手となる『週刊金曜日』編集長の本多勝一から招待券(同封の手紙を裁判書証として提出)が回ってきてのことであった。そこで配布された上映実行委員会作成の「参考資料」には、ランズマンの映画製作の基本的動機が、こう記されていた。
「反植民地闘争を共に闘った仲間が硬直した言辞と態度に立てこもり、アルジェリアの独立を支持した上でイスラエルの存続を支持することが可能だということを頑として理解しようとしないのに対する、ランズマンの反論でもあったのだ」
『なぜイスラエルか』(73)『ショア』(85)『ツァハル』[イスラエル国防軍](94)というランズマン「三部作」の題名を並べただけで、イスラエル支持の国策映画以外の何物でもないことは、最早、論ずるまでもないのだが、その後の上映運動では、こうした背景は宣伝されていない。意図的に隠していると批判されても仕方がない状態である。
映画製作には膨大な資金が必要である。ところが、本書でも指摘されているイスラエル首相(当時)、極右政党代表、元テロリストのメナヘム・ベギンが、八五万ドル(約一億二千万円)を出し、《この映画には国益が関わっている》と公言したことなど、日本人には、まるで知らされていない。
「映像芸術」などという言葉もある。「百聞は一見に如かず」ともいう。声や活字を越える情報伝達効果を否定するわけにはいかない。しかし、テレヴィ業界で二十数年を過ごした私自身の実感からいうと、写真といい、映画といい、テレヴィといい、その先祖の芝居といい、それぞれに負の歴史がある。いかにも真に迫る映像描写と音響効果で人を騙し、戦争を煽ってきたメディアでもある。嘘も付けるという基本的な問題点は、活字文化と同様なのだ。
最近発達した小型8ミリヴィデオは別として、映像作品を作るのには文章を書くよりも金が掛かる。それも手伝ってか、多くの映像作家には、一発屋の性格が濃厚である。真偽よりも刺激、深い歴史的背景よりも目前の表面的現象を追う一時的表面的性格が、活字メディアよりもさらに増幅される。真実の報道の道具としてよりも、デマゴギーの増幅役としての危険性の方が、より大きいメディアである。特に「記録映画」などと大書されている場合には、大いに疑って、眉毛にたっぷり唾を塗り込んでから、細部を注意して見る必要がある。ヴァーチャル・リアリティによる非論理的な仮想の認識の世界などいうものは、今に始まったことではない。おとぎ話以来のことなのだろうが、現在の映像作品には、さらに、想像力、ひいては批判力を眠らせてしまう効果さえある。
『ショア』に関しては、本書の中にも皮肉っぽい批判が、いくつか出てくる。手元には、フォーリソンが執筆した作品評など、詳しい資料もある。早い時期に総合的な批判をまとめたいと願っているが、とりあえず、本書で何度も強調される「証拠」の側面から、一応の補足をしておきたい。
アウシュヴィッツの焼却炉が出てくるが、焼却炉そのものの位置付けについては本書でも論じている。火葬を習慣とする日本にも、そこら中に焼却炉がある。発疹チフスの蔓延で急遽増設されたことは誰しも否定できないのだから、これだけでは、「ユダヤ人絶滅政策」の証拠にはなり得ない。しかも、アウシュヴィッツの第一収容所の病院の前にある「ガス室」と称される建物は、戦争中には防空壕だった。そこへ戦後、焼却炉を運んできて据え付けたのだということを、すでに博物館当局が認めている。粘土細工の「ガス室」などは何の証拠にもならない。実際に公開されている「ガス室」のデタラメ振りについては拙著『アウシュヴィッツの争点』を参照されたい。
怪しげな雰囲気のモノクロ画面に映し出される「トレブリンカ」の建物配置図についても、詳しい批判の論文がある。この配置図自体が、これも戦後の裁判の際に作られ、法廷に提出されたものである。本書にも出てくるカナダ人、ボールは、戦争中にアメリカ空軍が撮影した航空写真の分析で、この配置図よりも実際の方が、はるかに単純で、丸木の小屋しかなかったこと立証している。
配置図を前に説明する元SS下士官は、三千ドイツ・マルクで雇われたことが明らかになっている。証言についても、詳しい研究論文がある。近い内に訳出する予定である。
なお、この件でも、『世界』(95・8)「インタビュー/映画『ショア』ができるまで/ランズマン監督に聞く」という記事があった。要約すれば、本人に勝手にしゃべらせ、「証言」と検証なしの「俗論」を綴り合わせただけである。論評する気にもならないほどの、発表報道型、お粗末記事でしかない。これもマスコミ業界の実情の象徴であろう。
追記:以下の囲み文章はWEB公開当時の本文前の付記。2018.11.28下部に移動。