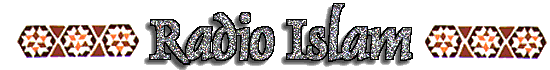第1章 神学的な諸神話
電網木村書店 Web無料公開 2000.2.4
第1節 “約束”の神話:
約束の土地か、征服した土地か?
《わたしはこの地をあなたの子孫に与える。エジプトの川から、かの大川ユフラテまで》(『創世記』15章18節)
政治的シオニズムの統一主義者の読み方
●一九九四年二月二五日、バルーフ・ゴールドスタイン医師が、長老の墓所で祈りを捧げていたアラブ人を虐殺した。
●一九九五年一一月二五日、イガール・アミールが、と“約束の土地”としての“ユダヤとサマリア”(現在のヨルダン川の西)をアラブ人に譲ろうとするものは誰であろうとも処刑することを誓う彼のグループ、“イスラエルの戦士”の指示の下に、イツァク・ラビンを暗殺した。
(a)現代のキリスト教による解釈
ジュネーヴのプロテスタント神学単科大学で旧約聖書を教えるアルベール・ドゥ・ピュリー教授は、博士論文を要約して一九七五年に、『ヤコブの年代の神の約束と宗教的伝説』と題する二巻の著書を発表した。その中で彼は、最も優れた歴史家の研究と現代の解釈を、取りまとめて検討し、その全体を見渡している。彼は特に、『父としての神』の著者、アルブレヒト・アルトと、『イスラエルの歴史』[関連文献は巻末資料に記載]の著者、マーティン・ノートに注目しており、つぎのように記している。
《贈物としての土地という聖書のテーマの起源は、“族長の約束”、つまりは、創世記の言い伝えに従うと、神が族長アブラハムに語った約束に発している。創世記の物語は、神が族長に約束し、族長の子孫がその後に住み着いた土地の所有について、何度も違った形で伝えている。サマリアとユダヤの地の主要な聖所、シケム(『創世記』12章7節)、ベテル(『創世記』13章14~16節、28章13~15節、35章11~12節)、マムレ(ヘブロンの近隣、『創世記』15章18~21節、17章4~8節)などでの宣言であり、これらの約束は、現在のパレスチナのすべての地域に適用されるようである。
聖書の語り手は、イスラエルの起源を、ある時代の限られた期間に引き続いた出来事として伝えている。すべての残された記憶、歴史、伝説、物語、詩などは、口伝てに語り継がれたものであり、ある特定の家系の年代記の枠組みの中に挿入されている。ほとんどすべての現代の解釈は、この歴史の大略の全体をフィクションと見る点で一致している。
アルブレヒト・アルトとマーティン・ノートの労作は、特に、引き続く年代の区分、族長時代、エジプト虜囚時代、カナンの征服などがフィクションであることを明らかにした》
アルベール・ドゥ・ピュリーの論文に従って、さらに現代の解釈の労作から要点を紹介すると、パリのプロテスタント神学単科大学の学長、フランソワーズ・スミス夫人は、その著書、『一九四八年以後のプロテスタント、聖書とイスラエル』の中で、つぎのように記している。
《最近の歴史的研究は、エジプトからの集団移住、カナンの征服、追放以前のイスラエル人の国家的統一、国境の細部に関する古典的な描写を、フィクションと認めることを余儀なくする。聖書の歴史編纂は、どう語っているかではなく、どう作ったかについて説明しなければならない》
フランソワーズ・スミス=フロランタン夫人は、一九九四年に発表した約束の神話についての著書、『不合理な神話/“約束”の研究』で、厳密な視点を提出した。
[族長の約束の起源]
アルベール・ドゥ・ピュリーは、以下のように続ける。
《ほとんどの聖書解釈者は、族長の約束の古典的な表現、たとえば『創世記』13章14-17節、『創世記』15章18~21節の表現を、イスラエル人によるパレスチナの征服、より具体的には、ダヴィデの治世下でのイスラエルの支配の拡大の「事後承認」のためのものと考え、また考え続けている。いいかえれば、約束が族長の物語の中に導入されたのは、この“先祖の時代”を、ダヴィデとソロモンの黄金時代の告示と序曲に仕立てるためだったというのである。
族長の約束の起源は、つぎのように限定して要約することができる。
1、土地の約束を、定住の約束だと考えると、それが初めて与えられたのは、それまでの放牧生活を止めて、定住が可能な地域での暮らしを望むようになった遊牧民の集団に対してのことである。この場合には、約束は、いくつかの異なる部族の宗教的および伝承的な世襲財産の一部になり得る》
原注:近東の宗教的聖句の知見が示すところでは、メソポタミアからエジプトに至るまで、ヒッタイトをも含めて、すべての民族が、彼らの神から土地についての同じような約束を受けている。
エジプトの場合には、トゥトゥモス3世(紀元前一四八〇~一四七五)が建てたカルナックの石碑によると、彼が、ガザ、メギド、カデッシュから、ユーフラテス流域のカルケミシュまでの遠征で得た勝利を祝って、神が、〈私は、この布告によって、汝に長く大きい土地を割り当てる。私は、ここに至り、汝に西の土地を撃つことを許す〉と宣言している。
“豊かな三日月地帯”の反対側のメソポタミアの場合には、『バビロニア創世記詩篇』の六枚目のタブレットの46節で、神マルドゥークが〈それぞれの分け前を定め〉、契約を固めるためにバビュロンと神殿の建設を命令している(『近東の宗教』)。
両者の中間に位置するヒッタイトの場合には、天上の女神アリーナに、つぎの歌が捧げられている。〈御身は天と地の平穏を見張り、この国の境界を定める〉(同前)
もしもヘブライが同じような約束を得ていなかったとしたなら、それは正真正銘の例外を構成する!(『贈物としてのパレスチナの土地』)
《2、遊牧民の約束の目的は、ある地域や国の政治的および軍事的な征服ではなくて、ある限られた領域内での定住にあった。
3、起源をたどると、『創世記』が語る族長の約束の相手は、“エクソダス集団”と一緒にパレスチナに入った神のエホバではなくて、カナンの神エルの三位一体の地域的分身である。土地の所有者である地域的な神のみが、彼の土地での定住を遊牧民に許可することができた。
4、その後、定住した遊牧民の氏族が他の氏族と連合して〈イスラエルの民〉を形成するに至ると、昔の約束に新しい次元が加わる。定住は、すでに果たされた目的となり、約束は以後、政治的、軍事的、"国家的"な支配領域の意味を帯びる。こうして、再解釈により、約束は、パレスチナの決定的な征服の予告、ダヴィデの帝国の正統性の告示として理解されるようになる》
族長の約束の内容
《羊飼いの氏族の定住化を目指す“遊牧民”の約束は、おそらく事件前に起源を持つものだが、〈国家〉規模に拡大された約束はそうではない。〈イスラエルびと〉という部族への統合は、パレスチナ定住以後のことにすぎないから、遊牧民の約束を政治的主権の約束だとする再解釈は、「事件以後」に行われたに違いない。だからして、〈エジプトの川(アリシュ渓谷)から、かの大川ユフラテの流れまで〉に位置するすべての地域と、そこに住むすべての民族への、選ばれた民の支配権を意味する『創世記』15章18~21節の約束は、明らかに、ダヴィデの征服に想を得て以後に、「以前の事件」へとさかのぼって創作した神託である。
解釈の研究は、〈遊牧民〉の約束の〈国家的〉な約束への拡大解釈を、族長の物語が初めて文字に記される以前の時期に確定することに成功している。
あるエホバ信者が、旧約聖書の最初の高位の語り手、またはむしろ、物語編纂者だと目されているが、彼が生きていたのはソロモンの時代だった。だから彼は、ダヴィデの栄光によって族長の約束が再解釈され、すべての希望の彼方へと実現されたかのような数十年間についての同時代人、および目撃証人であった。
『創世記』12章3節bは、エホバ信者の作品を理解する上で鍵となる章句の一つである。この章句によれば、イスラエルの祝福は必然的帰結として、“地のすべてのやから(adamah)[accent省略]”への祝福を含まなければならない。地のすべてのやからとは、パレスチナとトランスヨルダンでイスラエルとともに地を分かち合う住民のすべてのことである。
こういうわけでわれわれは、歴史上の何時いかなる時に、神がアブラハムという名の歴史上の人物の前に姿を現わして、彼にカナンの地を所有する合法的な権利を授けたものかどうかということを、確言できる立場にはない。法律的な視点から見ると、われわれは、"神"という署名のある土地譲渡証書などは、まったく所持していないどころか、むしろ、たとえば、『創世記』12章1~8節、13章14~18節などの情景が、歴史的な事件の再現ではないと信ずるに足る十分な根拠を握っている。
さらには、族長の約束の「現実化」ということが、あり得るのだろうか? もしも、約束の現実化が、所有の権利として役に立つとか、政治的な領土返還要求に奉仕するとかいうことを意味するのなら、疑う余地もなく不可能である。
いかなる政体であろうとも、約束の担保それ自体を根拠に領土返還を要求する権利は持ち得ない。
旧約聖書の約束が現在のイスラエル国家の領土返還要求を正当化するという考え方は、いかなる方法によっても、キリスト教徒の間での賛成者を得ることはできないだろう》
以上の文章は、一九七五年二月一〇日にスイスのクレ=ベラルで行われた会議におけるイスラエル・アラブ間の紛争の神学的解釈に関する討論からの抜粋である。原文は、一九七六年発行の『神学的および宗教的な研究』3号に所収されている。
(b)ユダヤ教の予言者による解釈
[土地と血に関する完全なデマゴギー]
(アメリカの「ユダヤ教のための連盟」の元議長、エルマー・バーガー法師の講演より)
《現在のイスラエル国家の樹立を、聖書の予言の遂行であり、それゆえに、イスラエル人が彼らの国家を創設し維持するために行ったすべての行為を、神が事前に承認したと称するなどということは、だれにも許してはならない。
現在のイスラエルの政策は、イスラエルの精神的な意味を破壊、ないしは少なくとも曇らせてしまった。
私は、予言の伝統についての基礎的な二つの要素の検討を提案する。
a、最初に、予言者はシオンの回復を訴えているが、土地それ自体が神聖な性格を持っているのではない。贖罪についての予言的概念の純粋で明白な基準は、神との契約の回復であり、それは、この契約が王とその民衆によって破られて以来のことなのである。
『ミカ書』では、このことをとても清らかに、つぎのような詩につづっている。
〈聞け、ヤコブのかしらたちよ。イスラエルの家のつかさたちよ。あなたがたは善を憎み、悪を愛し、……血をもってシオンを建て、不義をもってエルサレムを建てた。……それゆえ、シオンは田畑となって耕され、エルサレムは瓦礫の塚となり、神殿の山は偶像崇拝者の宮殿となる〉(『ミカ書』3章1~12節)
シオンは、神の法の支配なしには、神聖ではあり得ない。エルサレムで制定された法だからといって、そのすべてが神聖な法だということにはならない。
b、契約に関しての順守と忠実さが必要なのは、土地だけではない。シオンに再び住む人々のそれぞれが、神との契約に関しての正義、廉直、忠実さを求められる。
シオンの再興を願う人々は、条約、同盟、軍事力の行使またはイスラエルの隣人に優る軍事的支配などによってそれを達成しようと考えてはならない。
……予言者の伝統が明らかに指し示すのは、土地の神聖さを維持するものは、その土でもなく、ただそこに住むというだけの住民でもないということである。
唯一の神聖で、かつシオンに相応しいものは、人々の振舞いに表われる神との契約である。
それゆえ、現存のイスラエル国家には、約束の世紀への神聖な計画の実現を主張する権利は、いささかもない。……
イスラエル国家は、土地と血に関する完全なデマゴギーである。
いかなる民族も土地も神聖ではないし、この世のいかなる精神的な特権に値しない。
シオニストの全体主義は、すべてのユダヤ教徒を、暴力と軍事力で支配しようと望むものであり、ユダヤ教徒を、その他の人々と一緒にし、同じものにしてしまう》(『予言、シオニズムとイスラエル国家』)
[ラビン首相の暗殺はシオニスト統一主義者の論理]
イツァク・ラビンを暗殺したイガール・アミールは、不良少年でも狂人でもなくて、シオニストの教育の純粋な産物である。法師の息子で、テル・アヴィヴ近郊のバル・イランにある宗教大学の優秀な学生だった。タルムード学派の教えに導かれ、ゴラン高原の精鋭部隊の兵士となり、書棚には、数か月前にヘブロンの族長の墓で二七人のアラブ人を殺したバルーフ・ゴールドスタインの伝記を並べていた。彼はおそらく、イスラエルの国営テレヴィが組んだ大規模な特集報道で、“エイヤル”(イスラエルの戦士)グループが、政治的シオニズムの祖、テオドール・ヘルツルの墓の上で、と宣誓する有様を見たであろう。
ラビン首相の暗殺には、ゴールドスタインの殺人と同様に、シオニスト統一主義者の神話の厳しい論理が刻みこまれている。イガール・アミールの発言によると、殺せという指示は、ヨシュアの時代と同じくのである(『ル・モンド』95・11・8掲載AFP電)。
イガール・アミールはイスラエル社会の例外ではない。スペインの新聞、『エル・パイス』(95・11・7)の報道によれば、イツァク・ラビンが暗殺された当日、キルヤット・アルバとヘブロンの入植者たちは、バルーフ・ゴールドスタインの栄光を称えて建てられた霊廟を取り巻いて、ダヴィデの聖詩を歌いながら歓喜の舞踏を演じたのである。
イツァク・ラビンは象徴的な標的だったが、それは彼が、彼の葬式でビル・クリントンが言い張ったように、からではない。彼は、インティファーダが始まった時の占領軍司令官だった。彼こそが、その土地の古びた石ころ以外の武器を持たないパレスチナの土地の子供たちが、彼らの祖先の土地を守るために、その石ころを手に握って立ち上がった時に、という命令を発した張本人だったのである。
しかし、イツァク・ラビンは現実主義者だから、ヴェトナムでのアメリカと、アルジェリアでのフランスと同様に、一つの隊が別の一つの軍隊とではなくて、一つの「民族」全体と衝突する場合には、いかなる決定的な軍事的解決もありえないことを理解した。
そこで彼は、ヤセル・アラファトと、妥協点を探る作業を始めた。ただし、国連が非難している占領地の部分での自治権については譲歩するが、現地のアラブ人から奪い、ヘブロンのように憎しみの養成所と化した“入植地”については、イスラエル軍が守り続けるというのである。
だが、これだけでも、植民地主義支配の受益者たる統一主義者たちにとっては、行き過ぎも甚だしかった。彼らは、ラビンに対抗して"裏切り者"呼ばわりをし、暗殺という恥ずべき行為を導き出す雰囲気を作り上げた。
イツァク・ラビンが犠牲者となったのは、何万人ものパレスチナ人の犠牲者の葬列に続いてのことであり、“約束の土地”という神話、血みどろの植民地主義の数千年を経た古めかしい口実のためなのである。
この狂信者による暗殺が、いまさらながら示すのは、イスラエル国家が、一九四七年の分割で決められた国境の内側で安全を確保し、まったく独立したパレスチナ国家との間に真の平和を実現するためには、現在の植民地主義、つまりは、将来のパレスチナ国家の内部に存在し、絶えざる挑発と同時に将来の戦争の起爆剤の源泉となるすべての入植地の、根本的な除去が必要だということである。