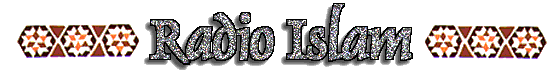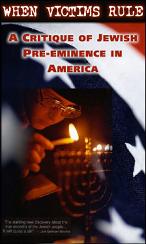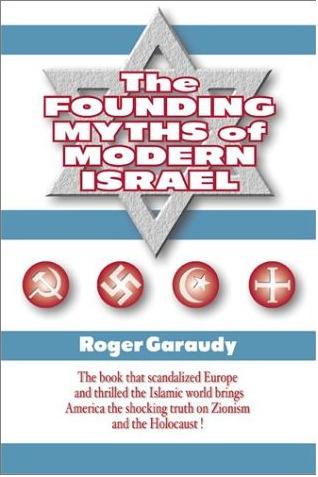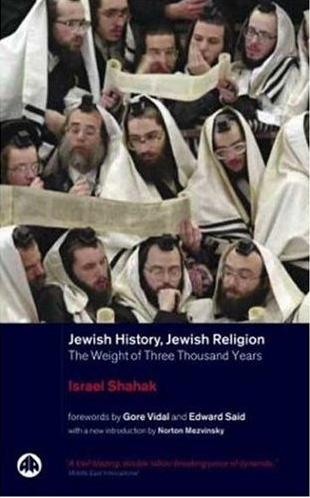『我が闘争(抄訳)』の全文
負傷して後送さる
一九一六年九月の末、私の属する部隊は、フランダースの南方ソンムの戦線に向って進軍を続けていた。そこに於ける戦争は実に物凄いものであった。戦争と云うよりも、まるで地獄のような有様であった。我々は銃砲火が文字通りに渦巻く戦場にあって、陣地の奪取に阿修羅のような悪戦を続けた押し戻されたり、跳ね返したりして、一寸の地を得るためにも死力が尽された。しかし我々は決して退却はしなかった。所謂死守した。
そのうち十月七日、遂に私は敵弾のために負傷した。そして陣地から一旦後方の野戦病院に運ばれたが、私の負傷は国内送還の必要があると云うので、複雑な精神状態のまま帰還することになったのである。
私は二年の間、全く戦争以外の何物をも見なかった。明けても暮れても、汚れ切った軍服と、砲弾の炸裂と、死を賭けての闘いとのみの中で過して来た私には、二年振りで見る祖国の姿をどう想像していいか分らなかった。軍服を着ていない人間の姿、そんなものは昔何処かの国で見た、遙かな思い出のような気さえもしたのである。
私は国境を越えてドイツへ入る前に、一旦エルミイスというところの病院へ運び込まれた。そしてそこで後送の順が回って来る迄を静かに横たえられていた。フト私は妙なる音楽の様な声が、隣りに伏している兵へ話しかけるのを聞いた。女! 女の声であった。二年間すっかり忘れていたドイツ婦人の声は、全く私をびっくりさせた。その女は看護婦ではあったが、とまれ私は二年間只の一度も耳にしたことのない女の声を聞いて、名状の出来ない気持を味わったことであった。
帰還列車はベルギー領をドイツの国境に向って走った。ブラッセル、ルウヴァン、リエージュ、これらの町々は嘗ての日我々が戦争への興奮に耳をほてらせながら、堂々と行進して通り過ぎた所である。誰の胸にも今は負傷兵として後送される自分と、健康な兵士であった頃との対照的な気持が沸き上がったに違いない。
愈々国境を越えて、懐かしい祖国へ入った時には、誰も彼も一様に興奮した。そしてあの夢にも忘れなかった高い破風と、特色のある鎧戸を持ったドイツの最初の家を見た時には、その興奮は頂点に達した。
おお、祖国! 懐かしのドイツ!!
顧みれば一九一四年の十月、この国境を越えて敵地へ赴く時の我々は、全身を熱狂的な興奮に燃え立たせていた。生きて再びこの国境を跨げるとは思わなかった。にも拘らず、傷ついたとは云え私は再び祖国を見ることが出来たのだ。そのことによって私は興奮した。しかしそれは静かな喜びの壺に盛られた静かな興奮であった。